動画制作の見積もりで失敗しない|内訳チェックリスト・社内稟議の通し方
動画制作
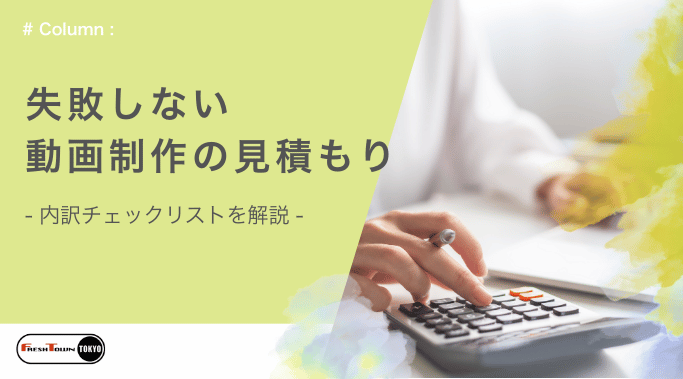
動画制作を初めて発注する企業にとって、「いくらかかるのか」「何を準備すべきか」「見積書はどこを確認するべきか」といった疑問は尽きません。特に中小企業や初めて動画を制作する担当者にとって、相場の理解不足が費用の無駄やトラブルを招くこともあります。
本記事では、動画の見積書で確認すべき内訳のチェックポイント、制作会社への依頼時の注意点、さらには社内稟議を通すための資料テンプレートまで、実践的な内容を網羅的に解説します。
読み終えたころには、「何にいくらかかるのか」「自社にとって適切な制作依頼の方法は何か」を把握でき、見積もりで失敗しないための判断軸を持てるようになります。
動画制作の費用はどう決まる?基本構造と内訳を理解する
動画制作の費用は、主に「企画」「撮影」「編集」など複数の工程ごとに分かれており、それぞれの工程に必要なスタッフ・機材・日数などによって構成されています。料金体系はプロジェクトの規模や目的に応じて大きく異なり、明確な「相場」が存在しないケースも少なくありません。
費用は、以下の3つの軸で決まるのが一般的です。
・ 制作内容の複雑さ(例:3DCGやアニメーションなど)
・ 関わる人数と役割(例:ディレクター、カメラマン、ナレーター等)
・ 納期と作業期間(例:急ぎ案件や長期プロジェクト)
また、スタジオ費用やキャストの出演料、BGMの使用料など、見落としがちな別途費用も発生します。見積書を見る際には、「費用項目がすべて記載されているか」「諸経費が適正か」などを必ず確認する必要があります。
映像制作にかかる主な費用項目とは?
映像制作における主な費用項目は、以下のように分類されます。
1.企画・構成
・ シナリオ作成、コンテ作成、演出設計など
・ ディレクション費、構成会議の打ち合わせ費用
2.撮影関連
・ 撮影スタッフ(カメラマン・アシスタントなど)の人件費
・ 撮影機材費(カメラ、照明、音声、ドローンなど)
・ ロケ地費用やスタジオレンタル、交通費、宿泊費など
3.編集・仕上げ
・ 動画編集費(カット編集、色補正、テロップ挿入など)
・ BGM・SE・ナレーション・MA作業などの音響処理
・ CG・モーショングラフィックス・3D加工費用など
4.出演・キャスティング
・ 演者、モデル、ナレーター、エキストラなどの出演費
・ ヘアメイク・スタイリストなどのサポートスタッフ費用
5.その他
・ 著作権・使用料
・ 納品形式に応じたDVD作成やデータ変換費用
・ 諸経費・管理費
こうした費用項目は、目的や用途によって選定すべき項目が異なるため、クライアントと制作会社との事前すり合わせが重要です。
企画から納品までの各工程にかかる費用
動画制作は多段階の工程で構成され、それぞれに異なるコスト構造が存在します。代表的な流れと費用の目安は以下の通りです。
1.企画フェーズ
・ 内容のヒアリングと目的設定
・ シナリオ構築、構成案の作成
・ 提案資料やスケジュール作成
▶費用目安:3〜10万円程度
2.撮影フェーズ
・ ロケやスタジオでの実写撮影
・ 撮影スタッフ、照明、カメラ機材などの準備
・ ヘアメイク、衣装、キャスト手配など
▶費用目安:10〜30万円以上(1日撮影ベース)
3.編集フェーズ
・ カット編集、テロップ挿入、音楽挿入など
・ ナレーション録音、MA処理、BGM・SEの調整
・ クライアントからの修正対応
▶費用目安:5〜20万円程度
4.納品フェーズ
・ 指定フォーマットへの書き出し
・ DVD・データ納品、クラウドアップロード
・ 修正後のマスターデータ制作
▶費用目安:2〜5万円程度
全体として、動画制作費用はシンプルなWeb用動画であれば20万円前後、テレビCMや高クオリティの映像では100万円以上に上ることもあります。予算内に収めるためには、工程ごとの役割と金額を明確にすることが必要です。
撮影・編集・ナレーションなど具体的な作成費の内訳
実写映像の制作では、以下の具体的な作成費が発生します。
撮影費用の内訳
・ カメラマン:5〜10万円/日
・ 撮影機材レンタル(カメラ・照明・音声):3〜8万円
・ ロケハン費、ロケ地使用料:1〜5万円
・ スタジオ費:5〜10万円
編集費用の内訳
・ 映像編集(カット・色補正・テロップ挿入):5〜15万円
・ モーショングラフィックス(2D/3D):5〜20万円
・ CG・アニメーション挿入:8〜30万円
・ 修正対応(回数や範囲により変動):別途見積り
音声関連の費用
・ ナレーター起用:3〜10万円(有名声優は高額)
・ BGM・SE:著作権フリー使用で1〜3万円、オリジナルは10万円以上
・ MA作業:3〜8万円程度
その他の追加費用
・ キャスト・モデル起用費:5〜30万円
・ ヘアメイク・スタイリスト:3〜8万円
・ 衣装・小道具:1〜5万円
これらの項目は「別途費用として見積書に記載される」ケースも多いため、事前の見積依頼時に確認しておくことが非常に重要です。映像制作の品質と予算のバランスをとるには、内訳の透明性が鍵を握ります。
動画の種類別で見る相場感
動画制作にかかる費用は、種類によって大きく異なります。用途・目的・制作形式によって必要な工程や人員、機材のレベルも変動し、それが見積もり金額に直接影響します。
特に企業が初めて動画制作を依頼する際には、予算感や一般的な価格帯を把握しておくことが大切です。
この章では、代表的な動画の種類ごとの相場感を解説します。動画の目的に合った適正な費用を見極めるための判断材料となるでしょう。
プロモーション動画・企業紹介動画・CMの相場感
プロモーション動画や企業紹介動画は、企業のブランディングや商品・サービスの訴求を目的として広く活用されています。
一方でCM(コマーシャル)動画は、短時間で強い印象を残す構成や演出が必要なため、より高度な制作力が求められます。
相場の目安
・ 企業紹介動画(3分程度):30〜80万円
・ サービス紹介プロモーション動画:50〜150万円
・ テレビCM(15秒〜30秒):100〜500万円
費用構成の特徴
・ 企業紹介動画では、自社内でのインタビュー撮影や既存素材の活用によりコスト削減が可能なケースもあります。
・ CM動画では、キャストの起用費用やスタジオ収録・演出が重視されるため、費用は比較的高額になります。
・ 短尺で高クオリティが求められるCMは、照明・音響・演出・編集すべてにおいてプロフェッショナルな対応が求められます。
アニメーション動画やイベント撮影の料金目安
アニメーション動画やイベント撮影には、異なるスキルセットや制作体制が必要とされます。特にアニメーションは、動きやグラフィックによる表現が中心となるため、表現手法や作成ツールによっても費用が大きく変わります。
アニメーション動画の費用目安
・ 2Dアニメーション(1分):10〜30万円
・ 3DCGアニメーション(1分):30〜100万円
・ モーショングラフィックス動画:15〜50万円
イベント撮影の費用目安
・ セミナー収録(1カメ・2時間):10〜25万円
・ 展示会・記録映像撮影:20〜50万円
・ ライブ配信(カメラ複数+スイッチャー):50〜150万円
コストに影響する要因
・ アニメーションは使用するイラストや動きの複雑さ、尺の長さ、修正の回数によって費用が大きく変動します。
・ イベント撮影は現場対応力や機材の数、撮影スタッフの人数がコストを左右します。
・ 配信や記録映像の場合、撮影だけでなく編集対応の有無で金額が増減します。
テレビ放映用・SNS広告用で異なる制作費の特徴
テレビ放映用とSNS広告用では、目的やターゲットが異なるため、制作スタイルも大きく変わります。それに伴い、費用構成や制作体制にも違いが出てきます。
テレビ放映用の特徴
・ 高画質対応・放送基準準拠が求められる
・ テレビ局との調整・字幕挿入・音声仕様など特殊工程が発生
・ 使用料や出演者契約など、制作後の費用も想定が必要
▶費用目安:100〜300万円(制作のみ)
SNS広告用動画の特徴
・ 短尺(15秒〜60秒)でインパクト重視の構成が主流
・ 縦型動画・字幕対応・スマホ最適化が必要
・ テンプレート活用や簡易撮影で費用を抑えられることも多い
▶費用目安:10〜50万円(用途とクオリティにより変動)
メディア別費用の違いまとめ
| メディア | 特徴 | 費用目安 |
|---|---|---|
| テレビCM | 品質重視、放送基準必須 | 100〜500万円 |
| SNS広告 | 短尺・縦型・高頻度運用向け | 10〜50万円 |
| Webサイト動画 | 汎用性高、企画の柔軟性あり | 20〜80万円 |
媒体により尺・品質・撮影規模が異なるため、発注時は目的と配信メディアに応じた提案を受けるのが適切です。
見積書で必ずチェックすべきポイント
動画制作を依頼する際、見積書の内容はそのままプロジェクト全体のコスト構造を表します。内容の確認を怠ると、予算オーバーや不要な費用の発生、あるいは納品後のトラブルにつながりかねません。
見積書には、どの工程に、どのくらいの費用がかかるのかを明確に記載する必要があります。また、項目の重複や抜け漏れ、曖昧な記載などは注意が必要です。
ここでは、見積書を確認する際に必ずチェックすべきポイントを具体的に解説します。
項目ごとの費用に抜け・重複はないか?
見積書の最重要チェックポイントは、費用項目の正確さです。以下のような点に注意が必要です。
確認すべき代表的なポイント
・ 企画・構成・撮影・編集・ナレーションなど、各工程が網羅されているか
・ 素材準備・出演者手配・衣装・照明・スタジオ費用など、発生しがちな追加項目が反映されているか
・ 二重計上(例:撮影機材費がスタッフ費用と別に計上されているなど)がないか
・ 単価×数量の合計が一致しているか
対応策
・ 一覧表形式で内訳を比較する
・ 前提条件(使用時間、出演者数、編集回数など)が明記されているかを確認
・ 自社内での費用チェックリストを活用する
こうしたチェックを怠ると、後から想定外の金額が発生する恐れがあるため、事前の精査が不可欠です。
人件費や諸経費の記載方法に注意
見積書には、スタッフの人件費や制作会社の諸経費がまとめて記載されることが多くありますが、その内訳が曖昧なままだと、コストの適正判断が難しくなります。
よくある課題
・ 「ディレクション費一式」「技術スタッフ費用一括」など、詳細が省略されている
・ 「諸経費10%」などとして一律で計上され、内容が不明
・ 撮影日数・編集回数など、工数ベースの算出根拠が提示されていない
チェックすべきポイント
・ 人件費は誰が・どのくらいの時間・どんな役割で関わるのかが明記されているか
・ 諸経費は交通費・通信費・消耗品費など、分類と金額の明示があるか
・ 「見積もり額が不自然に高い/安い」項目には、理由や条件を確認すること
必要に応じて、制作会社に見積の再提示や分解依頼をすることも有効です。
テンプレートを使った見積書作成のコツ
自社で見積書を作成・確認する際は、テンプレートの活用が非常に有効です。抜け漏れの防止、社内稟議通過率の向上、社外共有時の誤解防止など、多くのメリットがあります。
テンプレートに含めるべき項目
・ プロジェクト名・納期・制作期間
・ 制作工程ごとの費用項目
・ スタッフ構成と対応時間
・ 使用機材・場所・出演者の有無
・ 修正対応の回数や追加料金の発生条件
作成時のコツ
・ ExcelやGoogleスプレッドシートで編集しやすいフォーマットを使う
・ 備考欄を設けて、特記事項を明記
・ 複数社の見積りと比較しやすい構成にする
・ 自社にとって重要なKPIや費用対効果の指標も記載する
見積書テンプレートの活用により、社内外でのコミュニケーションが円滑になり、余計なやりとりやトラブルの回避にもつながります。
制作会社への依頼・交渉のテクニック
動画制作において、制作会社の選定と交渉スキルは、成果物の品質と費用対効果を大きく左右します。ただ安い会社に発注するだけでは、思っていたクオリティに届かない、社内で説明がつかないという結果になることも少なくありません。
実績や担当者の対応力、費用の透明性を見極めつつ、目的に合った発注内容を整理して伝えることが重要です。ここでは、制作会社とやりとりする際に意識すべきポイントを具体的に解説します。
実績のあるクリエイターやキャストを見極めるポイント
動画の品質は、制作チームのスキルや経験値に大きく依存します。どの制作会社も「実績あり」とはうたいますが、自社の目的に適した経験を持っているかを見極める視点が重要です。
確認すべき実績の見極め方
・ 自社と近い業界や用途(例:採用動画、サービス紹介、IRなど)の制作実績があるか
・ 制作事例に起用しているクリエイター(ディレクター・カメラマン・編集者)の名前が明記されているか
・ 過去の映像で構成・演出・表現方法に一貫性があるか
・ 出演者のキャスティング実績や、ナレーション・BGMのクオリティにも注目
さらに、実績のある会社であっても、担当ディレクターの経験値が浅ければ進行に支障をきたす可能性もあります。提案段階でのコミュニケーションも重要な判断基準になります。
見積もり依頼時に伝えるべき素材・構成・目的
見積り依頼の段階では、発注者側が伝える情報の正確性と具体性が、見積もり精度と制作内容の明確化に直結します。制作会社は提示された情報をもとに構成や工数を算出するため、曖昧な依頼ではコストにブレが生じます。
依頼時に伝えるべき情報リスト
・ 動画の目的(例:サービス認知、採用強化、展示会用など)
・ 想定する尺(長さ)、納期、配信媒体(Web、YouTube、テレビ等)
・ 既存素材の有無(画像・映像・ナレーションなど)
・ 必要な要素(アニメーション・ナレーション・出演者・撮影場所など)
・ 想定している予算の目安
・ 構成の希望や参考動画のURL
・ 撮影可能な日程・ロケ地の条件・使用用途の範囲
こうした項目を事前にテンプレート化しておくことで、依頼内容のブレを防ぎ、比較しやすい見積りを得られます。
適切な料金交渉と値引きの依頼方法
見積り金額を見たときに、「もう少し安くならないか」と感じることは多いですが、ただ安くしてほしいと伝えるだけでは信頼関係を損なう可能性もあります。交渉は、費用の内訳と制作目的に基づいて行うことが原則です。
効果的な料金交渉の方法
・ 「この工程は省略できないか」など、コスト削減の可能性を相談
・ 予算上限を提示したうえで、内容を再構成してもらう
・ 「この部分は自社で対応できる」などの役割分担を明示
・ 複数本発注や定期発注を見越した割引交渉
注意すべき点
・ 値引き交渉は一度だけに留め、追加の条件変更は避ける
・ 金額だけでなく、納品スピード・修正回数・サポート体制とのバランスを意識
・ 比較表を作成して各社の対応を可視化することで、判断材料が増える
「安くする」ではなく、「目的に合った最適なプランを提案してもらう」という姿勢が、結果的に良い制作物と関係性を生みます。
フレッシュタウン社ならワンストップ対応・見積無料はこちら
制作会社選びに悩んでいる方は、企画から納品、運用サポートまでワンストップで対応できる会社を選ぶと、やりとりの負担軽減や品質の均一化につながります。
たとえば「フレッシュタウン社」では、以下のような特徴があります。
フレッシュタウン社の強み
・ 無料の見積もり対応(初回ヒアリング・プラン提案込み)
・ 撮影・編集・ナレーション・アニメーションなどフル対応
・ 専任ディレクターによる工程管理と品質管理
・ テンプレート提供や社内稟議資料の作成サポートも可能
もし、動画制作や企画をご検討でしたら、お気軽にご相談ください。ヒアリングのうえ最適な進め方と御見積もりをご提示します。
稟議書の通し方と社内説明用テンプレート
動画制作においては、見積もりが高額になりやすいことから、稟議の通過が最大のハードルとなるケースも多く見られます。特に中小企業や大企業の現場部門では、費用対効果を説明する社内資料の質が、承認可否を左右する大きな要素となります。
このパートでは、稟議通過を前提に設計された費用説明の方法と、すぐに使えるテンプレート例について紹介します。明確な構成と根拠を持った資料を提出することで、社内の意思決定をスムーズに進めることが可能になります。
説得力ある費用説明資料の作り方
稟議に通すためには、単なる見積もりの転記ではなく、「なぜこの費用が妥当なのか」を説明できる構成にする必要があります。費用を「投資」として捉えてもらうための工夫が求められます。
費用説明資料に含めるべき内容
・ 動画制作の目的・背景
- 採用強化、営業支援、認知拡大、商品理解促進など
・ 期待される効果・KPI
- 問い合わせ件数、応募数、資料請求率、商談数の増加など
・ 相場比較
- 他社の事例や一般的な価格帯との比較(価格帯の妥当性を説明)
・ 内訳の明確化
- 制作項目別に金額を記載し、不要なコストが含まれていないことを示す
・ ROIの試算
- 投資対効果(例:1本50万円の動画で100件のリードを獲得→リード単価5,000円)
ポイント
・ 目的に対して必要な制作要素を簡潔に記載
・ 視覚的な表や図を活用して伝わりやすさを強化
・ 不明瞭な項目には注釈や補足説明をつける
稟議通過率を高めるための構成と文言
稟議書で重要なのは、「意思決定者が一目で納得できる構成」と、「予算の正当性を伝える文言設計」です。冗長にならず、読みやすく説得力のある構成が求められます。
稟議書のおすすめ構成
1. 案件名・目的の明示
- 例:「採用活動強化に向けた企業紹介動画制作」
2. 動画制作の必要性と背景
- 自社の課題、解決手段として動画が有効な理由
3. 見積概要と金額
- 総額、主な費用項目、支払い条件
4. 比較検討結果(任意)
- 他社との比較、金額・対応・納期の違いなど
5. 期待される成果・KPI
- 明確な効果指標、評価方法
6. 添付資料
- 見積書、構成案、制作会社概要など
稟議文面で使える表現例
・ 「費用対効果の高い施策として、短期的な成果が期待されるため提案します」
・ 「動画活用による応募数の増加が見込まれ、早期に投資回収が可能です」
・ 「目的に対して、最低限必要な制作内容に絞って構成しています」
すぐ使える社内提出用のテンプレート紹介
稟議資料を一から作成するのは手間がかかります。以下のようなテンプレート形式を活用することで、抜け漏れを防ぎ、スムーズに社内申請が可能になります。
稟議書テンプレート
【稟議書】
■件名
企業紹介動画制作の発注について
■起案者
部署名:〇〇部
担当者:氏名(〇〇)
■提案内容
採用広報活動の強化を目的として、自社の魅力を伝える企業紹介動画を制作したく、本稟議を起案いたします。
■背景・目的
・ 採用サイトおよびYouTubeチャンネルでの掲載を想定
・ 自社の働く環境や社員インタビューを通じた応募者数増加を図る
・ 現場のリアルな声を通じて、企業理解とエンゲージメント向上を狙う
■制作内容(動画概要)
・ 尺:約3分
・ 構成:インタビュー+社内風景+ナレーション+BGM
・ 納品形式:MP4/クラウド納品+サムネイル画像提供
■費用内訳(見積書添付あり)
| 項目 | 金額(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 企画構成費 | ¥50,000 | 構成案、台本作成、演出打合せ含む |
| 撮影費 | ¥150,000 | カメラマン1名、機材一式、1日撮影 |
| 編集費 | ¥120,000 | カット編集、テロップ、色補正、BGM挿入 |
| ナレーション費 | ¥50,000 | プロナレーター起用・録音・MA処理含む |
| 諸経費 | ¥30,000 | 交通費・管理費・クラウド納品費用等 |
| 合計 | ¥400,000(税抜) | ※税込¥440,000 |
■支払条件
納品後、翌月末支払い(請求書発行ベース)
■効果・期待値
・ 月間応募者数:前年比+20%を想定
・ 動画再生回数:初月1,000回以上を目標
・ 企業イメージの向上、エントリー率改善に寄与
■比較・補足事項
複数社より相見積もりを取得し、以下理由により当該制作会社を選定
・過去に同業界での実績あり
・構成力と納期対応の柔軟性
・予算内での最適提案
■添付資料
1.見積書(PDF)
2.提案書(動画構成案)
3.制作会社プロフィール資料
以上、承認のほどよろしくお願いいたします。
テンプレート作成のポイント
・ ExcelまたはWordで作成し、社内フォーマットに合わせて調整
・ 上司・決裁者が読みやすいように要点を簡潔に記載
・ 添付資料は1ファイルにまとめ、PDF形式で提出
これらのテンプレートを整備しておけば、急な依頼や複数案件にも迅速に対応できる体制が構築できます。
まとめ:成果につながる動画制作のために費用と見積りを正しく把握しよう
■無駄なく、効果的な動画制作を実現するには「費用の見える化」と「判断基準の明確化」が不可欠です。
動画制作は、目的や用途に応じて必要な工程・人材・機材が大きく異なるため、費用構造も一律ではありません。費用が発生する理由や内訳を理解し、納得感を持った発注判断を行うことが重要です。
以下のような視点を押さえておくことで、社内外の調整がスムーズになり、動画の成果最大化につながります。
☞動画制作を成功させるための重要チェックリスト
1. 動画の目的を明確にする
- 採用、販促、ブランド向上など目的により必要な構成が異なる
2. 制作費用の内訳と相場を理解する
- 各工程ごとの費用構成を把握し、相場と比較検討する
3. 見積書は内容・項目・計算根拠を精査する
- 抜け・重複・不透明な諸経費などがないか確認
4. 制作会社の選定基準を明確にする
- 実績、対応力、見積内容、提案力で総合判断する
5. 交渉時には依頼内容を具体的に伝える
- 構成案・素材・納期などを明示し、見積り精度を高める
6. 稟議を通すための社内説明資料を整備する
- テンプレートを活用し、目的・費用・効果を簡潔に伝える
動画制作は「ただ作る」だけではなく、企業の伝えたい価値を正しく届けるプロジェクトです。そのためには、見積りや請求のやりとりも単なる事務作業ではなく、成果に直結する重要なプロセスと捉える必要があります。
本記事の内容を参考に、費用・交渉・社内説明すべてのフェーズで適切な判断を行い、納得のいく動画制作を実現してください。
よくあるご質問
質問:動画制作の費用はどのような項目で構成されますか?
回答:
動画制作の費用は、企画・構成、撮影(機材・スタッフ・キャスト)、編集(映像編集・音声・テロップ)、ナレーション・BGM、納品形式、ロケ地費、衣装・ヘアメイク、管理費・諸経費など多岐にわたります。見積書にはこれらの項目が明細化されていることが望ましく、用途や目的に応じて変動します。
質問:アニメーションと実写映像では費用にどのくらい差がありますか?
回答:
一般的に実写映像は撮影・演者・スタジオなどの物理的コストが発生するため、短尺であれば比較的コストが抑えやすいです。一方でアニメーション(特に3DCGや複雑なモーション)は制作工数がかかるため、長さによっては高額になることもあります。表現方法と目的に応じて適切な形式を選ぶことが重要です。
質問:初めての依頼で見積書をチェックする際の注意点はありますか?
回答:
初めての依頼では、「一式」や「別途」といった曖昧な表現に注意が必要です。また、撮影機材や編集作業の内訳、修正回数の上限、納品形式などが明記されているか確認しましょう。特に前提条件や費用発生のタイミング、支払いサイトに関する情報は事前に確認することでトラブルを防げます。
質問:社内稟議用の動画制作資料に含めるべき要素は?
回答:
稟議資料には、目的・背景、費用の内訳、相場比較、期待される効果(KPI)、スケジュール、添付資料(見積書・構成案)などが含まれていると効果的です。また、テンプレートを活用し、表や図を使って直感的に理解できるよう構成することで、稟議通過率を高めることができます。
質問:制作会社選びで確認すべき比較ポイントとは?
回答:
価格だけでなく、過去の実績、対応範囲(企画から納品まで対応可能か)、担当者のコミュニケーション力、見積もりの透明性、納期の柔軟性などが重要です。また、複数の制作会社から見積もりを取得し、構成や内容を比較することで、コストパフォーマンスの高い選定が可能になります。

この記事を書いた人
株式会社フレッシュタウン
屋外広告・動画制作と展示会ブース制作の2つの事業をメインにお客様のプロモーション支援を行っております。


